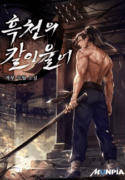Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha RAW - chapter (195)
心を保つため
『
渉
が、病院に───』
声もなく胸中で呟いた言葉を最後に、
愛華
は
圭
との会話どころではなくなった。真相を確かめるべく今すぐ駆け出したい衝動に駆られるも、圭がそっと愛華の腕に手を添えて首を横に振る。ホームルームを控えた彼女たちに自由はなかった。覚束ない指先でスマホの画面をなぞり心配している旨を渉に連絡しようとするも、病院に向かう理由も分からないままでは切り出し方すら分からなかった。
「……」
「あ、愛ち……落ち着こ?」
よほど落ち着きがなかったのだろう、その場で忙しなくソワソワする愛華を圭が落ち着かせる。愛華はそんな親友の心配そうな眼差しに動きを止め、しょんぼりと下を向いた。
「心配だよね、そうだよね」
「……うん」
歩みを合わせるような言葉に、愛華はようやくひとまずの落ち着きを見せる。気が付けば席に座らされていた。後ろから圭の腕が愛華を包み、
逸
る心にそっと真綿のマフラーを巻き付けられる。
「さじょっちだもん、大丈夫だって」
「……うん」
耳元でそっと囁かれる声。気を収められた自覚がある愛華は理性をもって素直に首肯する。こんな時に人の温もりを享受している場合ではないと心が抗う反面、血の気が引いた首元を暖められる心地好さを否定できなかった。
机の上をジッと見つめながら、愛華は過ぎ行く時間が遅くなるのを感じた。
◇
「
佐城
くんだけど、ちょっと怪我しちゃったみたいで病院に向かいました。もう少しで無事に文化祭を終えられたのに、残念ね」
「怪我……」
愛華が待ち侘びたホームルーム。担任の
大槻
から語られた真実により、渉の容態について一つ情報を得られた。想定していた複数のケースの中で最も最悪と言える真実だった。さしものクラスメイトもここでおちゃらける者は居なかった。
「はい、それじゃ明後日からの話だけど───」
話題はすぐに別の連絡事項へ。大槻により空気が重くならないようにコントロールされた。
掌
の上で転がされた生徒たちはすぐに平常心を取り戻す。そして話題はこの後に控えたおじさん職員たちとの飲み会の愚痴へ────笑みを浮かべる半数以上の生徒の頭からは既に渉の話は消えていた。
ホームルームが終わって解散が告げられると、愛華のもとに圭と
佐々木
がやって来る。その後ろを困惑気味の
斎藤
舞
が追いかけた。交際を始めたばかりの彼氏が、ホームルームを終えていの一番に他の女子のもとに向かうのだからその胸中は複雑だろう。
「
夏川
……打ち上げ、どうする?」
「ぇ……」
それは佐々木なりの気遣いだった。曲がりなりにも愛華を想った事がある彼は、愛華が近しい存在の怪我を忘れて楽しめるような女の子ではないことを知っていた。逡巡するにしてもその迷いは短く、どう考えても楽しめると思えなかった愛華は参加しない方向に心が傾く。
それに対し、親友が待ったをかけた。
「愛ち……行こ? たぶん、じっとしてる方がモヤモヤすると思う」
「圭……」
親友の主張、それはどうせ自分たちにできることはないのだから、せめて何かをし続けることで少しでも心の負担を減らそうというものだった。佐々木もその考えに同調している。
「そうね……わかった。私も行く」
「うんっ、よかった!」
心配する気持ちも、その優しさも、いつでも相手に届けられるわけではない。どうせ届かないのなら、心配し続けることが渉の負担になると思うことにした。
(……そうだ)
わずかばかりの活力を取り戻した愛華は、同じく渉と関わりの深い存在である
一ノ瀬
深那
に目を向ける。愛華の席の反対側、廊下側の窓際の席に座る彼女は、ホームルームを終えたというのにまだ座り続けていた。
(あれ……?)
きっと渉の怪我を知って放心状態になっているのだろう。それは理解できる。しかし、一人のままでいる姿に愛華は首を傾げる。普段は寡黙な彼女だが、二学期に入ってからは常に誰かに構われるほどの人気ぶりであるはずなのだ。
そんな深那のもとに愛華は向かう。
「一ノ瀬さん……大丈夫?」
「!? えっ……ぁ……」
肩に手を置いた瞬間、ビクリと体を震わせる深那。すぐに愛華だと気付くと、我を取り戻したかのように周囲を見回す。
「ホームルーム、終わったよ」
「あ……」
愛華の予想通り、深那は自由になった事に気付いていなかったようだ。それを自覚したのか肩を竦めてから恥ずかしそうに視線を落とした。何となくそれに至るまでの経緯や気持ちを察している愛華は、先ほど自分にされたものと同じ問いを深那に投げかける。
「一ノ瀬さん。打ち上げ、どうする?」
「……」
この少女の胸中が、もし自分と同じだとするなら。心の負担を減らすためにも圭から勧められたように深那も打ち上げに来るべきだろう。そう思った愛華は多少、強引にでも深那を連れていこうと考える。文化祭が始まる前、深那が打ち上げに参加するよう他のクラスメイトから駄々をこねられていたことを知っている。
少女は、揺れる瞳で愛華を見上げ───。
「わ、わたしっ……アルバイトがあるのでっ!」
「あっ……」
思っていたより俊敏な動きで立ち上がった深那は愛華が予想していなかった言葉で断りを入れると、サブバッグを持ってパタパタと走り教室から出て行った。返す言葉に迷ったこともあり、引き留めるため手を伸ばすのが遅すぎた。
「大丈夫かな……」
「優しいね、愛ちは」
心配そうにする愛華を、愛おしそうな目で見つめて微笑みながらやって来る圭。深那からきっぱりとフラれた事も相まって、顔を赤くすることしかできなかった。
◇
予約されていたカラオケ店の大部屋。参加するクラスメート全員が入るには少し窮屈だが、文化祭の後ということでそもそも
鴻越
高校の生徒が詰め寄せていた。見慣れた制服の生徒が、店内のいろんな部屋を行き来している。佐々木はサッカー部の先輩にヘッドロックされ連れて行かれた。
歌ってノッて騒がしい室内。愛華の口角も自然とその雰囲気に引っ張られて上がる。愛華はテンションが上がっても騒ぐタイプではない。そのためじっとソファーに座って両手でドリンクのグラスを握っているだけだったが、明るくない気持ちを吹き飛ばすには十分すぎるほどだった。
そんな中、ややしっとりとした前奏が流れ出す。誰もが知ってるような女性ボーカルの曲だ。待望の女子の出番がやって来て、室内の男子が爆発的に盛り上がる。
「愛ち! 歌おっ!」
「えっ!? ええ……!?」
圭によりグラスをテーブルの上に置かれ、腕を引っ張られる愛華。急な誘いに困惑しながら皆の前に引っ張り出され、どこからともなく新たなマイクが回ってきた。
圭から始まった歌い出し。Aメロを終えると、愛華はおそるおそる遅れないように歌い出す。度重なる妹への子守唄で磨き上げた囁くような声に、男たちは
暫
しの休憩と言わんばかりに落ち着いて耳を傾けた。カラオケ恒例の光景である。
そういえばラブソングだ、と気付いて顔を赤らめたのは歌い終わった後の話。
「ほっ……」
女子のターンが続いて騒がしさが多少収まり、体を動かしたわけでもないのに愛華はソファーに座ってひと息つく。圭は別の場所で誰かが膨らませたパーティーグッズの風船をスパイクして男子の顔に打ち付けていた。
そんな折、机の上に置かれていたいくつものスマホがパッと点灯する。愛華のものも例外ではなかった。拾い上げて確認すると、クラスのメッセージグループに新着メッセージが届いた通知だった。
【行けなくてごめん。ドジった】
通知画面に収まる短いメッセージに、愛華は目の色を変えてスマホのロックを解除する。すぐに連絡しようとするも、グループメッセージは渉の一言を皮切りに次々と更新された。手持ち無沙汰になってスマホに指を滑らせるクラスメイトは少なくなかった。
【大槻ちゃんから聞いたよ。だいじょうぶ?】
【おつかれ。どこ怪我したん?】
【なんか居ないと思ったわ】
「う……」
一日の中で愛華がスマホを触る時間はそんなに多くはない。スマホ中毒な同級生の素早いフリックや口火の切り方に付いていけないのは当然の帰結だった。言葉を選んでいる間にグループの更新は加速していく。しかも訊きたい事を代わりに訊いてくれるものだから余計に発言のタイミングを逃してしまう。
【手の平。片付けしてたら工具がぶっ刺さっちゃって】
「ぁ……」
周囲からどこともなく「うわっ」と小さな悲鳴が聞こえる。渉の言葉を映像で想像してしまったようだ。それは愛華も例外ではなかった。患部を押さえられず、もう片方の手で手首を握って苦悶の表情を浮かべる一人の男の子。膝から崩れ落ち、再起することもなく床に頬を擦り付けて呻く一人の男の子。誰かに運ばれて行くその様子まで、愛華の頭の中で嫌なほど鮮明に映像が作り上げられていく。堪らず、スマホを自らの胸に押し当てていた。
【マジかよ】
【痛そー】
【大丈夫だって。入院するほどじゃないし】
そんな言葉、信用できない。
アプリのメッセージから声は聞こえない。表情を読み取れない。ただ指先を動かすだけで放たれる言葉にどれだけの真実があるというのだろうか。
スクッ、と立ち上がった愛華に視線が集まる。部屋の扉までの動線、何かを察したクラスメイト数名がソファーに深く沈む。その前を、愛華は足早に駆け抜けた。